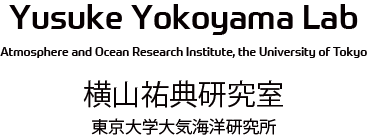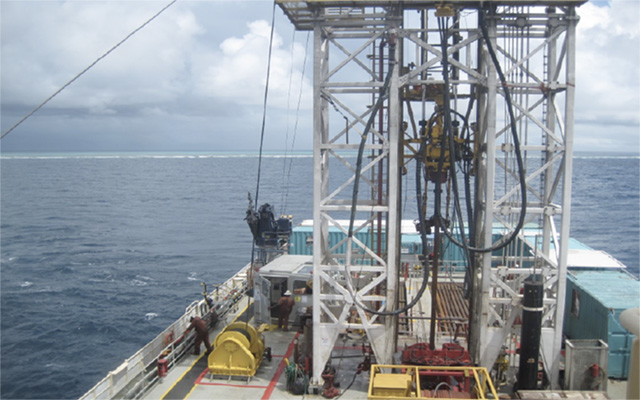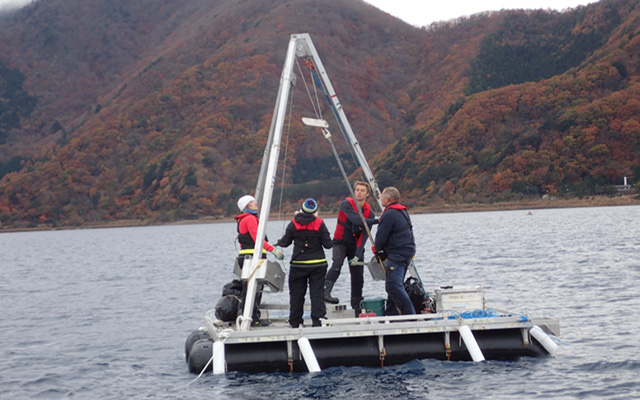News
2025.10.1 横山祐典教授が2025年アメリカ地球物理連合(AGU) フェローに選出されました
横山祐典教授が、アメリカ地球物理連合(American Geophysical Union; AGUと略す)の2025年の連合選考委員会によりフェローに選出されました。これは、同教授の長年にわたる「氷床の安定性と海水準および環境変動研究」に対する功績が評価されたものです。
横山祐典教授は、同所の海洋地球システム研究系の系長として研究を推進するとともに、本学のFSI事業「亜熱帯・Kuroshio研究教育拠点の形成と展開 -亜熱帯化する日本のベースライン評価と生物圏・人間圏の研究-」の統括責任者として奄美地域を核とした共同利用・共同研究のプラットフォーム「亜熱帯・Kuroshio研究教育拠点」の立ち上げにも携わってきました。
世界最大の地球・宇宙科学協会であるAGUは、卓越した貢献を果たした選ばれた個人に対し、毎年この栄誉を授与しています。1962年の創設以来、毎年選出されるフェローはAGU会員の0.1%未満です。AGUは世界148カ国に約50万人以上の会員を持つ、世界最大の地球物理学の学会です。AGUでは、地球惑星科学への貢献のあった会員をフェローとして選出しています。2025年には同教授を含む52名のフェローが選出されました。
受賞者は、2025年12月15日~19日にルイジアナ州ニューオーリンズで開催されるAGU25年会にて表彰される予定です。AGU25のテーマ「Where Science Connects Us(科学が私たちをつなぐ場所)」を反映し、表彰式では科学の継続的な進歩を示す画期的な業績を称え、その物語と成功がAGUコミュニティに刺激を与えることが期待されています。なお、横山教授は2018年にアメリカ地質学会(Geological Society of America; GSA)のフェローにも選出されており、AGUとGSAの両学協会でのフェロー選出は、2000年以降では日本人で唯一です。
2025年AGUフェローについて
https://www.agu.org/honors-home/announcement/union-fellows![]()
2025.5.18 地球惑星環境学国際研修II参加者追加募集のご案内
2025年9月1日から6日にかけて開講が予定されている集中講義「地球惑星環境学国際研修II」につきまして、定員に若干名の空きがありますので参加者を若干名追加募集いたします。 4月15日に行われました本講義の説明会の録画は以下のURLよりご視聴いただけます。ご興味のある方はぜひご覧いただき、参加をご検討ください。
https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/rec/share/sHiTbTQ3FptZbfYZSEC8r7NGJjNjGy8znfovxCs_TAHN_MgQMyoJ-TV7ZESprRfX.u3opUan1UQ-KIe9R?startTime=1744686924000
説明会の映像の中で一点訂正がございます。
録画内の「参加登録フォームへのQRコード・リンク」に誤りがありますので、以下の参加登録フォームのアドレスより参加登録をお願いいたします。
地球惑星環境学国際研修IIは、オーストラリア国立大学(ANU)から来訪する学生約15名とともに、日本国内の自然災害に関連する施設や地質学的な露頭等の巡検を通して国際的な学びを得ることを目的とし、実際のフィールドワークをANUの学生と共に行うことで国際的な研究の仕方を学んでいく研修となっています。
全学部全研究科の学部生(3.4年生)大学院生(修士課程・博士課程)が対象です。 なお、第一次募集期間中に受講希望者数が定員に満たなかったため、今回の追加募集では単位認定はありませんが、学部1.2年生のオブザーバー 参加も認めます。 参加費用はまだ確定はしていませんが5万円程度の予定です(交通費宿泊費込み。ただしこの他に現地で各自で調達する場合の昼食代等が必要です) 本集中講義への参加を希望される方は以下のURLより参加登録をお願いいたします。
【参加登録フォーム】 https://forms.gle/QceJdMofCJqczFX47
追加募集の締切りは6月20日(金)17時です。
その他何かご質問等がある場合はお気兼ねなく、本講義の担当教員 横山(yokoyama@aori.u-tokyo.ac.jp ) 本講義のTA レゲット(kaileggett@g.ecc.u-tokyo.ac.jp)までお問い合わせください。
2025.4.25 横山教授が取材されたガリレオXが明後日放送予定!
明後日4月27日(日)朝8時28分〜放送の「ガリレオX」(BSフジ)で、横山先生が今年3月加速器棟などで取材された様子が放映されます!お楽しみに!
※再放送5月4日(日)朝8時28分〜
[ガリレオX 黄砂は“悪者”か? 微細な粒子がもたらす被害と恵み]
2025.4.4 Yuning Zengさんが一高賞を受賞
9月に総合文化研究科の博士課程を終了されたYuning Zengさんが一高記念賞を受賞しました。
Yuning さんは9月卒業ですが一高記念賞の発表は3月のため、帰国されてからの発表となりました
ちょうど今月から実験のために来日されているため、賞状を直接お渡しすることができました。
おめでとうございます!
2025.1.6 D2Miyaさんが令和6年度岩手県三陸海域研究論文学生の部特別賞を受賞しました!
D2のZihan Huang (Miya)さんが令和6年度岩手県三陸海域研究論文学生の部特別賞を受賞しました!詳細については、以下のウェブページからご覧ください。
2024.11.12 亜熱帯Kuroshio研究教育拠点の形成と展開事業・市民参加による海洋総合知創出手法構築プロジェクト合同普及講演会「自然科学と社会科学の奄美群島(クロスポイント)」の開催
亜熱帯Kuroshio研究教育拠点の形成と展開事業・市民参加による海洋総合知創出手法構築プロジェクト合同普及講演会「自然科学と社会科学の奄美群島(クロスポイント)」を開催します。参加ご希望の方は以下のQRコードから参加登録をお願いします。Amami普及講演会_2024_ 配布用
亜熱帯・Kuroshioプロジェクト
亜熱帯・Kuroshioプロジェクトの紹介ページ・お問い合わせはこちら
地球惑星環境学 国際研修 International Excursion 2019〜
2019年〜2024年の東京大学とオーストラリア国立大学の合同巡検の様子をレポートとして配信していますので、ぜひご覧ください!
・2023年9月 ・2023年2月 ・2022年9月 ・2022年2月 ・2021年2月 ・2020年2月 ・2019年9月 ・2019年3月
研究室キーワード (Keywords):
地球化学、気候変動、海洋環境変遷、加速器質量分析計(AMS)、宇宙線生成核種、年代測定、表面照射年代法、ウラン非平衡年代法、化合物レベル放射性炭素年代法、有機地球化学、微量金属、サンゴ骨格、氷床コア、樹木年輪、堆積物コア、統合国際深海掘削計画(IODP)、第四紀、最終氷期、最終氷期極相期(LGM)、完新世、南極氷床、西太平洋暖水塊、南シナ海、タヒチ、グレートバリアリーフ、アタカマ砂漠、水月湖、日本海、アジアモンスーン、エルニーニョ南方振動、海洋大循環、海水準変動、地形、太陽活動、地磁気、銀河宇宙線
Geochemistry, Climate Change, Marine Environmental Change, Accelerator Mass Spectrometry (AMS), Cosmogenic Nuclides、Absolute Dating, Surface exposure dating, Age Determinations by Utilizing the Disequilibrium (Uranium Systems), Radiocarbon Dating, Organic Geochemistry, Trace Metal, Coral Skeleton, Ice core, Tree ring, Sediment Core, International Ocean Discovery Program (IODP), Quaternary Period, Last Glacial Period, Last Glacial Maximum (LGM), Holocene, Antarctic Ice Sheet, Western Pacific Warm Pool, South China Sea, Tahiti, Great Barrier Reef, Atacama Desert, Lake Suigetsu, Japan Sea, Asian Monsoon, El Niño-Southern Oscillation, Large-scale Ocean Circulation, Sea-level Change, Topography, Solar Activity, Geomagnetism, Galactic Cosmic Rays